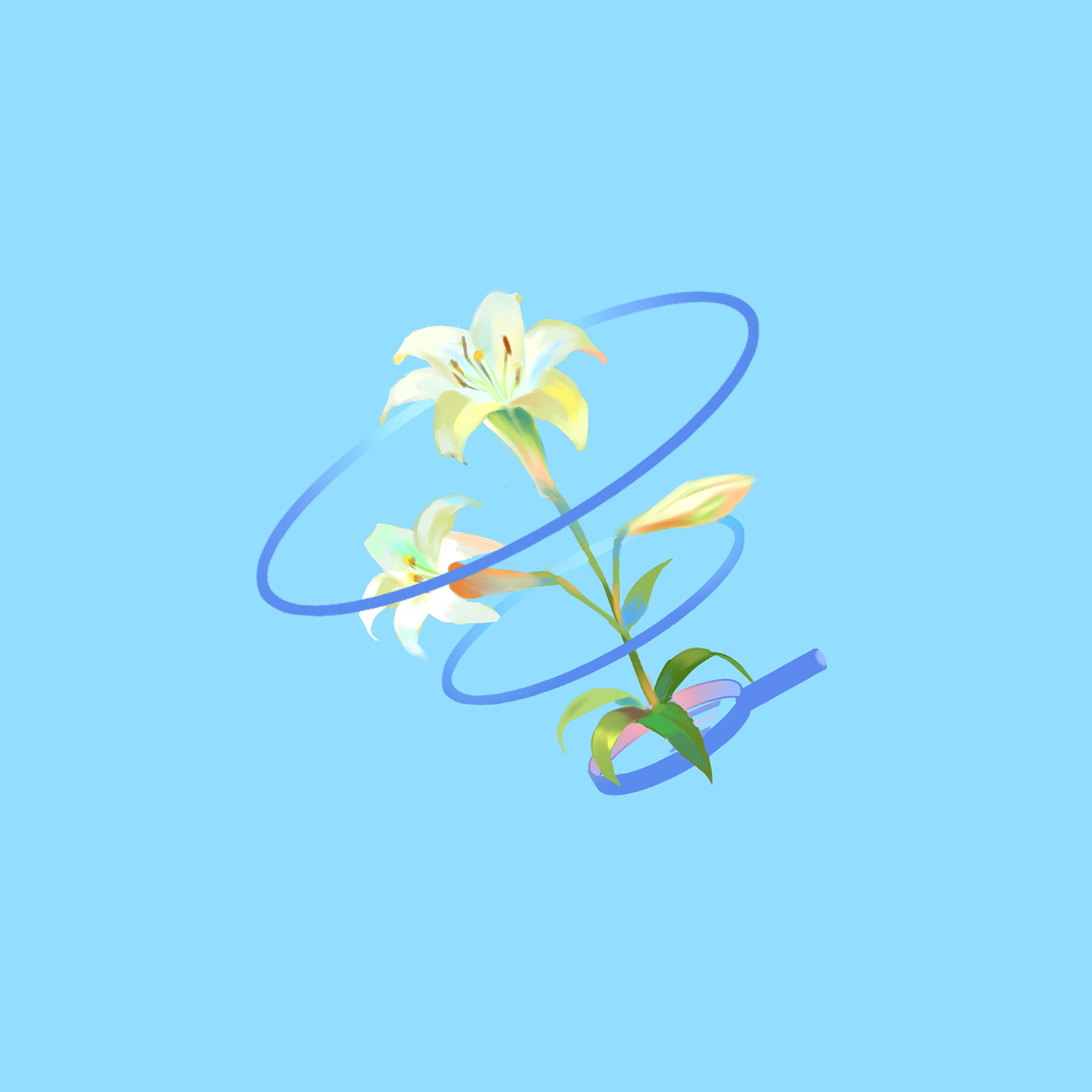こんにちは、アドプラットフォーム事業部でアナリティクスエンジニアをしているucchi-です。
ピクシブでは社員向けの情報発信やコミュニケーション促進のために「社内ラジオ」という社内番組を運営しています。 本日は社内ラジオを1年間運営し続けて得た気付きや知見をシェアします。
背景
新型コロナウイルスでリモートワークが進む中で、社内コミュニケーションの場が減り、社内の情報共有の機会が失われる、という課題がありました。
そこで、社内の情報共有の場所を増やすため、2021年2月に社内ラジオという社内番組がスタートしました。
社内ラジオの詳細
社内ラジオはGoogle Meetライブストリームを用いて社員向けに配信する番組です。
発表者(社員)が自発的にチームの成果やドメイン知識などを持ち寄って発表しています。
全社員が参加する会議が終わった後、毎週水曜の昼12:00〜12:45に放送しています。
視聴は任意でアーカイブ再生も可能ですが、約半数のメンバーがリアルタイム視聴しています。運営はucchi- javakky karaageの3人で回しています。

実際の配信画面はこのようになっています。VTuberの配信のような、ワクワクする番組を目指しています。

発表ジャンルについて
社内ラジオでは、自社プロダクトや法律、スキルなど業務に直接関係のある発表に加え、クリエイターやVRの理解を深める内容や福利厚生の活用方法など、幅広いジャンルの発表が行われてきました。以下過去の放送タイトル抜粋です。
- プロダクト・プロジェクト
- 「4年目のネット流行語100」持続可能なプロジェクト進行と裏話
- ドメイン
- VRChatユーザーとアバター改変
- 組織・制度
- z-channelについて

配信を支える技術について
ピクシブでは普段からMeetやSlack、Discordを使っています。
社内ラジオはこれらのコミュニケーションツールを用いることで配信を実現しています。
詳細は割愛しますが、例えば発表者が自宅から発表を行う際は以下のような配信構成になります。
配信構成は複雑になってしまいますが、発表者は普段慣れ親しんでいるツールを用いて発表できるので負荷を下げることが出来ます。

社内ラジオを1年間運営して何が変わったか
継続的な改善を通して番組の質が上がりました。
開始直後はMeetで発表内容をそのまま映すだけだった社内ラジオですが、社内ラジオ専用のイラストやBGMを作ったり、Slackの実況チャンネルを配信に載せたりすることで、より双方向でワクワクする配信が出来るようになりました。

また配信事故の経験を知見として積み上げたり、Notionを整備して配信や発表者向けのマニュアルを整備することで配信構成や手順が洗練されました。
このような工夫をしながら放送を継続することで、社内認知度や視聴者数が上がりました。当初の視聴者数は80人程度でしたが、現在は全社員数の約半数にあたる110人を常に上回っています。これは約5割の社員が視聴していることになります。
リモートワークが浸透するなか、気軽な情報発信や交流の場所として定着してきたのだと思っています。
社内ラジオを1年間運営し続ける秘訣
運営を続ける中で様々な苦労がありましたが、最も大切なのは発表者を集め続けることです。
社内ラジオは自発的に発表をしてくれる人たちによって支えられています。
それぞれの本業がある中で、事前準備や発表に膨大な時間を割いてくれる事に感謝しつつ、発表予定者を常に絶やさないことが肝になってきます。
発表者を集め続けるための施策は以下の2つに分かれます
- 発表意思を持つ人を増やす
- 発表意思を持つ人のうち、実際に発表してくれる人の割合を増やす
発表意思を持つ人を増やすためには、間口を広げるアプローチと、発表のハードルを下げるアプローチがあります。
前者については、業務に直結する発表だけでなく、クリエイターやVRの理解、福利厚生の活用方法などより多様なジャンルの発表事例を作ることで、社内ラジオで話せる話題の広がりを作っています。
後者について、事前にスライドを綿密に練り上げて発表頂くのは準備が大変です。スライドではなくNotionを見ながら発表したり、スケッチブック片手に対談形式でフリートークするなど、発表者の負担が少ない発表形式の事例を作っています。
発表意思を持っていても、実際に発表をするのは勇気がいると感じる人は多いです。発表意思を持った人を見つけるため、社内ラジオはslackのリアク字チャンネラーを使って”radioチャンス”というスタンプが押されると通知が飛んでくる仕組みを運用しています。その通知を見て、運営側が発表を行う際の不安点について説明をしにいきます。
また、名前とタイトルさえ記入すれば発表の予約が完了するようにしています。これにより立候補のハードルを下げています。

発表者が立候補したことを忘れないよう、直前にリマインドを行っています。 Slackのワークフロー機能を用いることで抜け漏れのない案内を行っています。

ツール・自動化を使うことで、運営コストを下げつつ参加コストを下げて発表者を継続的に集め続けています。
終わりに
社内ラジオを聴いてみたい方、社内ラジオで発表してみたい方はこちらをクリックしてみてください。 https://www.wantedly.com/companies/pixiv/projects